仕込みを終えて、店が静かになる。エスプレッソマシンの熱が抜け、床に置いた椅子がきしむ小さな音だけが残る夜。私は一人で『地底探検』を再生した。
映画を観る時間は、私にとって読書と同じだ。ページをめくるように、光と影をゆっくり受け取る。今夜の気分は、とにかく静か。洞窟の壁が返す足音の反響が、耳の奥にしばらく残った。
──ここから物語は、19世紀末のエジンバラへ。地質学者サー・オリヴァー・リンデンブルックが、溶岩の塊から“アルネ・サクヌッセンム”(16世紀のアイスランド人の学者/錬金術師で、地底行きの“先達”。ルーン文字で手がかりを残した、という劇中設定)の手がかりを見つけ、アイスランドのスナイフェルス火山から地底へ降りる道を信じて旅に出る。
弟子のアレック、装備の主である未亡人カーラ、そして寡黙な案内人ハンス(相棒はアヒルのガートルード)。一行は、夏至の影が示す火口から、ゆっくりと世界の下へ降りていく・・・
出典:X
あの作品をいま見直すたびに思うのは、科学の知識が物語の楽しさを奪うどころか、むしろ輪郭をはっきりさせてくれるということだ。地球内部は地殻・マントル・外核・内核の四層に分かれ、人類が掘り進めた最深部はおよそ十二キロ。現実に“巨大な空洞”はない——そんな現在の常識を知っているからこそ、映画が提示する「もしも」の外形線が、かえってくっきり見えてくる。
──地下は迷宮だ。水が尽き、絶体絶命に見えたとき、ハンスが岩の“汗”や風の向きを読み、地下水脈を探り当てる。印の刻まれた壁をいくつも抜け、巨大キノコの森を経て、一行は地下海の岸辺に出る。
筏を組み、風を受け、暗い水平線へこぎ出す。足音の反響はやがて波音に変わり、内側の静けさと外の不穏が同居する。
出典:どらごんづ☆Movie’z – FC2
今夜いちばん心を動かしたのは、荒れたアトランティスの遺構をじっと見せる場面だった。崩れかけた柱、砂に半ば埋もれた装飾、手入れされないまま呼吸をやめた街の気配。そこには時間の重さが沈殿していて、画面が静かに光っていた。
──地下海は荒れ、巨大生物の影が水面下を横切る。筏は打ち上げられ、そこに広がっていたのが、まさにこの地底のアトランティス。
引用元:どらごんづ☆Movie’z – FC2
サクヌッセンム本人の遺骸も横たわり、地底の時間が現実になる。野望に取り憑かれたサクヌッセム伯爵(サクヌッセンムの子孫)は一行を裏切り、装備を奪い、ガートルードをも失わせる。音を立てず進んできた旅路が、ここで軋むようにひずむ。
出典:ameblo.jp
五十代のいまの私は、正直、恐竜にはもうあまりワクワクしない。派手な“見せ場”としての生物は、たしかに客席を揺らすのだけれど、今日の私には、荒廃した都市の沈黙や、鉱物の微光のほうが届く。恐竜の群れは、遺跡の細部や、未知の鉱物/微生物のふるまいといった静かな驚異に置き換えられてもよかったのではないか。地底世界は、派手さより「静けさ」で深くなる。
それでも私は、巨大な空洞という“嘘”は残しておきたい。現実には崩れてしまうはずの空間が、もし本当に広がっていたら——行ってみたい、と今でも思う。そこには、物語がくれる純粋なロマンがある。
──出口はふいに近づく。帰路を塞がれた一行は、遺構にあった巨大な石の“皿”に火薬を仕込み、天井をこじ開ける賭けに出る。爆発が火山活動を呼び込み、祭壇皿ごとマグマに押し上げられた彼らは、遠くストロンボリ火山の火口から海へと噴き出す。船に救われ、地上に還ると、喝采の中で旅は静かに締じられる。探究心を失わない教授と、未来の予感を宿した若いふたり。地底の冒険は終わっても、地上の生活はまた続いていく。
映画は光の芸術だ。理屈で説明できない明るさも、画面に説得力があれば先へ進める。足音が壁に跳ね返り、わずかな光が水面を走り、人物の影が岩肌に滲む。その連なりを、私は読書のように一人で味わうのが好きだ。常連さんと閉店後に観る楽しさもあるけれど、この作品はやはり“独りの時間”が似合う。
観終えて、私は何もせずにしばらく座っていた。コーヒーを足すことも、ノートを開くこともしない。ただ、耳の中の反響が静まるのを待つ。やがて椅子を一脚ずつ元の位置に戻し、ホールの明かりを落とす。今夜の一行日記を書けと言われたら、こうなるだろう——「静けさの底で、古い冒険の埃がゆっくり光った」。
明日は月曜日、仕込みはあまりないし、おそらく暇だろう。
科学が教えてくれる現在地と、物語が連れていく遠回り。その両方を行き来できる夜は、店をやっていてよかったとしみじみ思わせてくれる。
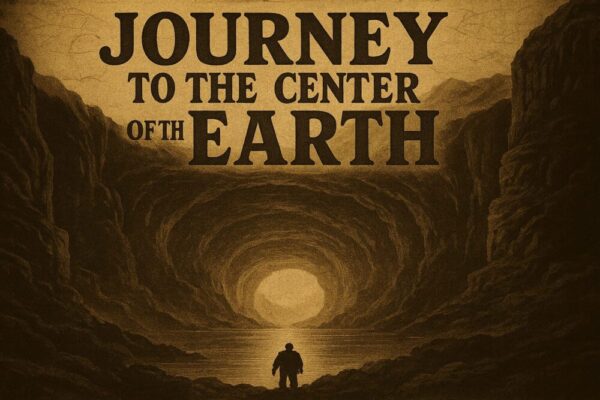






コメント