フジテレビのドラマ「ミステリと言う勿れ」第4話で、雨の中、記憶を失った爆弾犯・三船三千夫が主人公の久能整に向かって一篇の詩を朗読する場面がある。三好達治の「乳母車」である。

「ラストがいいよな」と呟く三船の表情には、言葉にならない深い哀しみが滲んでいた。
「乳母車」は、1930年に発表された詩集『測量船』に収められた三好達治の代表作である。「母よ――」という呼びかけで始まるこの詩は、「淡くかなしきもののふるなり/紫陽花いろのもののふるなり」と続き、目には見えない悲しみが静かに降り注ぐような情景を描き出す。
そして詩の終わりで、主人公は悟るのだ。「母よ 私は知つてゐる/この道は遠く遠くはてしない道」と。この旅は、母のもとへ帰る道ではなく、母から永遠に遠ざかっていく道であることを。
母よ――
淡くかなしきもののふるなり
紫陽花いろのもののふるなり
はてしなき並樹のかげをそうそうと風のふくなり
時はたそがれ
母よ 私の乳母車を押せ
泣きぬれる夕陽にむかつて
轔々と私の乳母車を押せ
赤い総ある天鵞絨の帽子を
つめたき額にかむらせよ
旅いそぐ鳥の列にも季節は空を渡るなり
淡くかなしきもののふる
紫陽花いろのもののふる道
母よ 私は知つてゐる
この道は遠く遠くはてしない道
ドラマの中で三船が「ラストがいい」と言ったのは、まさにこの最後の一節が、彼自身の人生と重なるからだろう。
三船は幼い頃に母が家を出て、父親や親戚からも愛情を受けられずに育った。小学校ではいじめに遭い、6年生の時に母が亡くなる。唯一の支えは4年生の時の担任の先生だったが、後にその先生こそが実の母だったと知る。
母は彼に「3は神聖な数字」と教え、名前に「三」の字を残していた。母への思慕、失った悲しみ、そして自分だけの大切な記憶を守りたいという思い──それが彼を爆弾事件へと駆り立てた。

「この道は遠く遠くはてしない道」という詩の結末は、母との別離、届かない愛情、そして果てしない孤独を象徴している。三船にとって、この一節は自分の人生そのものだった。母を求めても決して届かない。けれど、その想いを抱いたまま生きていかなければならない。詩が描く「はてしない道」は、三船が歩んできた、そしてこれからも歩き続けるであろう、孤独な旅路なのだ。
実は、この詩の作者である三好達治自身も、複雑な生い立ちを持っていた。詩集『測量船』は世間から絶賛され、三好を一躍有名な詩人にしたが、不思議なことに本人は後年、この詩集を「すべて消し去ってしまいたい」と語っている。世間の評価と作者の言葉の間にある大きな隔たり。それは単なる謙遜ではなく、三好自身の深い心の葛藤を物語っている。
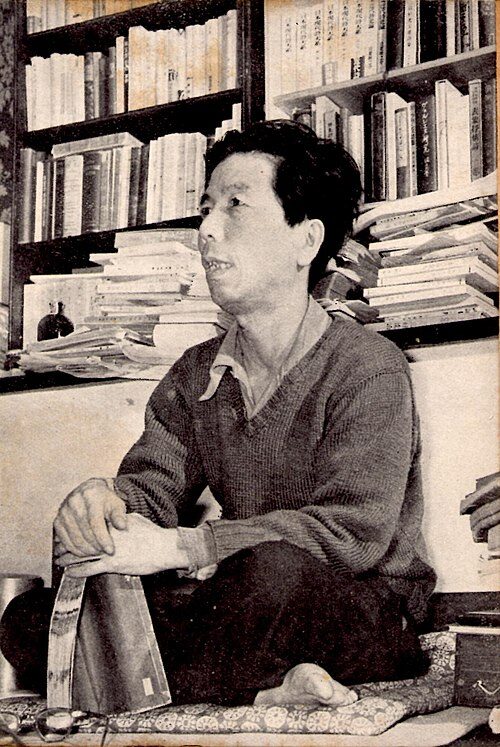
「乳母車」には、触れると壊れてしまいそうな繊細な心が描かれているが、それは三好のつらい幼少期の体験と深く結びついていた。大人になった彼にとって、あまりにも率直に自分の心の痛みを映し出した若い頃の作品は、正面から向き合うには苦しすぎたのかもしれない。
詩をもう一度読み返すと、その構造の見事さに驚かされる。詩は三つの段階を経て展開する。まず、静かな悲しみに包まれた風景の描写。次に、「母よ 私の乳母車を押せ」という激しい命令形の叫び。そして最後に、「この道ははてしない道」という諦念に満ちた気づき。子供時代への退行、現状への反逆、そして運命の受容──この三段階の心の変化が、読者の心を強く揺さぶる。
特に印象的なのは、「赤い総ある天鵞絨の帽子」という具体的なイメージである。これは失われた幸せな子供時代の象徴であり、つらい現実から心を守るためのお守りのようにも見える。空を渡っていく鳥のように季節は容赦なく過ぎていくのに、自分だけが取り残されている。その孤独感が、詩全体を貫いている。
ドラマ「ミステリと言う勿れ」は、この詩を単なる引用として使うのではなく、物語の核心に据えた。「母との距離感」「過去と向き合うこと」「喪失と再生」というテーマが、詩の言葉と共に深く描かれている。三船というキャラクターを通して、視聴者は三好達治の詩が持つ普遍的な力を再発見したのだ。
三好達治は、フランスの詩人ボードレールや師である萩原朔太郎から影響を受けながら、独自のスタイルを築いた。西洋の詩の「骨格」を借りて、そこに自らの体験という「血肉」を注ぎ込むことで、彼は外国の模倣ではない、深く日本的で、まったく新しい詩の世界を創り出した。「紫陽花いろ」という曖昧な色彩、「たそがれ」という物悲しい時間、「轔々と」という音の響き──これらはすべて、日本語でしか表現できない繊細な感覚である。
詩集のタイトル『測量船』とは、詩人が人間の心の深さという広大な海を「測量」する船である、という比喩だ。「乳母車」という詩は、母を失った悲しみや孤独という心の領域を、言葉という精密な機械で測量した、貴重な航海記録と言えるだろう。詩人という「測量船」が、魂を乗せた「乳母車」の進む「はてしない道」を記録していく。そう考えると、この一篇の詩が詩集全体の壮大なテーマへと繋がっていくのが分かる。
「乳母車」が伝えるメッセージは二つある。一つは、過去の心の傷は決して消えない、という厳しい現実。しかしもう一つは、その悲しみを「詩」という美しい形にすることで、人は苦しみを乗り越えることができる、という希望である。詩を作ることで、痛みは消えなくても、美しい作品へと姿を変えることができる。これは、喪失の中から意味を生み出す、人間の精神の強さの証だ。
ドラマの三船も、そして詩人の三好達治も、母への届かない思いを抱えながら、それでも生きていかなければならなかった。「はてしない道」を歩き続けることの苦しさと、同時にその道を歩むことでしか得られない何かがある。三船が「ラストがいい」と言ったのは、この詩が自分の孤独を肯定してくれたからではないだろうか。悲しみは消えないけれど、それでも歩き続けることに意味がある。その真実を、この詩は静かに、しかし力強く語りかけている。
雨の中で朗読された「乳母車」の一節は、ドラマの中だけでなく、視聴者の心にも深く刻まれた。100年近く前に書かれた詩が、現代のドラマを通して新たな命を吹き込まれ、再び多くの人の心を揺さぶっている。それこそが、優れた文学作品の持つ力なのだろう。母を想う気持ち、届かない愛情、そして果てしない孤独──これらは時代を超えて、人間の普遍的なテーマであり続けるのだから。


コメント